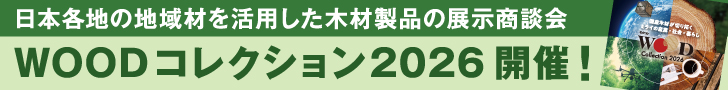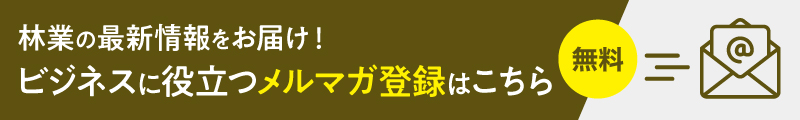【イベントレポート】社内林業大会で「業務円滑化」&「楽しい職場」へ!
2025/07/14

高性能林業機械の導入が目覚ましい林業現場。しかし確かなチェーンソーワークがフォレストワーカーの基本スキルであるのは今も変わらない。そんな中、現場で磨いたチェーンソー技術を社内で競い合うユニークなイベントが開かれた。その狙いとは?
1.チーム対抗戦!3種目で技術を競う
2.社内コミュニケーション促進業務円滑化と技術向上へ!
3.競技は真剣、採点は厳格盛り上がりは最高潮!
4.若手が手作りで企画運営!自主性尊重が会社成長の鍵
チーム対抗戦!
3種目で技術を競う
大会を開いたのは山梨県の八ケ岳山麓を施業エリアとする有限会社天女山。今年で創業67年を迎え、現在は15人の現場作業員が造林保育から素材生産、特殊伐採、森林環境教育まで幅広く手掛けている。従業員のほとんどが県外からの移住者だ。

「天女山林業大会」と名付けられた催しは5月上旬の平日に山梨県北杜市の同社の土場で第1回目を開催。1チーム5人編成の3チームによる対抗戦で実施し、「受け口作成」「丸太合わせ切り」「丸太早切りリレー」の3種目で競った。
各チームはいずれも同社の3つの部署の部長クラスを筆頭に、中堅から若手まで部署横断的なメンバーで編成。3種目とも持ち点100の減点方式とし、競技終了までに掛かった時間や正確性、安全性などを総合評価して採点した。
社内コミュニケーション促進
業務円滑化と技術向上へ!

チェーンソーワークの国内競技会といえば、2年に一度開かれる日本伐木チャンピオンシップ(JLC)が日本を代表する大会だ。「天女山林業大会」も「受け口作成」や「丸太合わせ切り」など、JLCを参考にして競技内容やルールが設定されている。
それでは事業体独自の林業大会の狙いは何か。山梨県内の「緑の雇用」研修生の講師や山梨県林災防の専任講師を務めるなど、安全対策の普及と実践に力を入れる同社の小宮山信吾社長はこう話す。
「弊社は『素材生産・造林保育』『特殊伐採』『営業企画・森林環境教育』の大きく3つの部署を設けています。ここ5年程で社員数が約1.5倍に増え、仕事の幅と量が増えるととともに、業務の細分化と専門化も進みました。
一方で従来の家族ぐるみのような雰囲気が薄れ、部署が異なるスタッフ同士の交流が大きく減ったのも事実です。毎週一回の朝の全体ミーティングすら、現場の都合で出られない班も出てきました。
しかし例えば植え付けや下刈りなどで忙しいときには、他部署のスタッフに応援を頼むこともあります。こうしたときには日頃からコミュニケーションが取れていないと現場が円滑に回りません。イベント感覚で楽しみながら親睦を深めて技術を競う。これが大会の一番の目的です」。
競技は真剣、採点は厳格
盛り上がりは最高潮!

伐倒精度を競った受け口作成競技。
今回の大会で大きく盛り上がった「受け口作成競技」では、高さ約2.5メートル、胸高直径30センチ程度の丸太を垂直に立て、そこに深さ7センチの水平切りの受け口を作る課題が設定された。
会合線の不一致は5点減点、制限時間(120秒)を過ぎると1秒ごとに1点減点、さらにレーザーポインタを使って15メートル離れた目標物に対する左右のずれを測り、2センチずれるごとに1点減点などの厳しい採点基準が設けられた。いずれもJLCのルールを参考にしている。
大会は終始アットホームな雰囲気で進められたものの、競技中は小宮山社長と全社員に一挙手一投足を注視されるだけに、緊張して臨むスタッフも多かった。
しかし若手の競技中には、同じチームのメンバーが冗談を言って肩の力を抜かせたり、ベテランのミスには他チームのメンバーがやじや突っ込みを入れて笑いを作り、場の空気を和ませたりするなど、会場では終始笑いと歓声が絶えなかった。
素材生産や造林保育を手掛けるフォレストマネージメント事業部の葛原司部長は「お祭りのような雰囲気で社員全員が楽しんだ一方で、単なる『おふざけ』にはならず、競技中は全員真剣そのものだったことが印象的でした。部署横断的なチーム編成による対抗戦にしたことで、メンバー同士が互いにカバーし合いながら優勝を目指し、会社全体のチーム力向上に大きなプラスになったと思います」と話す。
若手が手作りで企画運営!
自主性尊重が会社成長の鍵
天女山では4年程前までは離職者も多く、社員の定着が課題だった。しかし「ここ数年は大卒の若者や異業種から転身した50代などが相次いで入社しているものの、離職者は出ていません」(葛原部長)という。
背景の一つとして同社が見ているのが、今回の林業大会のような社員自発型の企画を積極的に後押しする職場環境の醸成だ。同社では使い古した刈払機の刃を文字盤にした時計や木の実を使った工作などを社員の発案で制作。
他にも同社が中心となって毎年夏に開く住民参加型交流イベント「山存(やまぞん)」でワークショップを開いたりするなど、社員の興味や得意分野を事業に積極的に取り入れる動きをここ数年、重視してきたという。
今回の林業大会は、もともと小宮山社長が発案したものだが、企画運営は入社3年目の高橋廣次さん(24)と、入社6年目の津端浩司さん(39)が自発的に担った。

「企画運営に携われて手応えを感じました!」有限会社天女山 高橋廣次さん
高橋さんは「入社後にJLCの動画を観て、かっこよくて自分も出場したいと強く思いました。JLCへの出場は正直まだハードルが高いですが、その第一歩として大会の企画運営に携われたことで、大きな手ごたえを感じました。来年の大会では枝払い競技も導入したいです」と話す。
受け口作成競技で使う丸太直立用の治具は、自動車用ジャッキを使って作るなど、他の社員もそれぞれの得意分野を生かして協力し、開催にこぎつけたという。

自動車用ジャッキなど身近な資機材を活用し、なるべくお金を掛けずに開催された。
「好天なのに丸一日、すべての現場を止めるのは、なかなか難しい選択だったのは事実です。ただ社員のモチベーション向上や働きやすい職場づくりといった広い視野で見ると、会社として大きなプラスにつながったと実感しています。来年もぜひ続けたいです」と小宮山社長は手ごたえを話す。
会社の成長とともに、もっと楽しく、そして働きやすい職場へ――。従業員の定着率向上が林業界の課題となる中、社員の自主性を会社成長の鍵ととらえる天女山の試みは多くの事業体の参考になりそうだ。
天女山林業大会のポイント

<開催の目的>
・コミュニケーション機会創出による業務円滑化
・技術向上
・安全対策の徹底
・イベント的な楽しみの創出
<行った工夫>
・部署横断的なチーム編成
・厳しいルール設定で競技のクオリティ維持
・若手に企画運営を一任
・身近な資機材の活用で経費削減
<期待される効果>
・部署を超えたチーム意識の醸成
・自主性尊重によるモチベーション向上
・職場への定着率向上
・JLC出場へのきっかけづくり
文:渕上健太
FOREST JOURNAL vol.24(2025年夏号)より転載