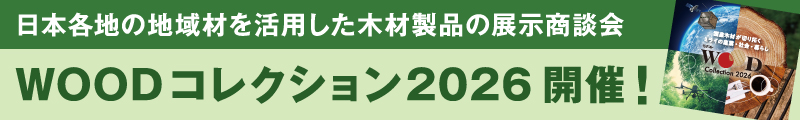森林クレジット制度における「ふたつの壁」とは? 先駆者に聞く、実践的な運用の工夫
2025/08/22

複雑で、ハードルが高いと思われがちな森林クレジット制度。だからこそ重要なのは、「できるところから、少しずつはじめる」ことだ。奈良県で最大規模のJ-クレジット森林管理プロジェクトに取り組む、大和森林管理協会の松山充事務局長に、制度との向き合い方と、実践的な運用の工夫について伺った。
多くの山主が、森林経営を
負担だと感じている
日本の林業の発祥の地とされる奈良県・吉野地方。500年以上続く独自の「密植・多間伐・長伐期施業」によって、高品質な吉野スギ・ヒノキを育ててきた。
「そうした歴史的背景もあり、奈良県では今でも大規模な森林を所有する山主が多い」と指摘するのは、一般社団法人・大和森林管理協会の松山充事務局長だ。同協会では、そうした山主をサポートするかたちで、地域森林の経営管理に携わってきた。

吉野林業は室町時代から続く日本最古の「人が作った山林」。密植・多間伐といった独自技術により、長い期間にわたり手間を惜しまず木を育て森を造ることで、他に類を見ない高品質な吉野スギおよび吉野ヒノキを生産してきた。
そのなかで松山さんたちが痛感したのが「大規模な山林所有者であっても、森林を管理経営していくことに、大きな負担を感じている」という事実だった。そこで木材販売に依存しない、新たな収益源を確保するためにスタートしたのが、森林クレジット制度を活用した「吉野林業プロジェクト」だ。
森林クレジット制度における
「ふたつの壁」とは?
現時点で、このプロジェクトには11人の山林所有者が参画している。管理者である大和森林管理協会がプロジェクト実施者となり、森林クレジットの認証を取得した。一見すると大規模な取り組みに見えるが、実は当初は、より多くの所有者の参画を見込んでいたという。
「ハードルになったのが、認証対象期間の長さでした。当プロジェクトの対象期間は16年。永続性の担保措置として、さらにその後10年間、森林経営計画などの提出が求められます。そこまで長期的に、森林経営を継続できるのか、と不安を感じる山主さんも少なくありませんでした」。
登録プロセスのなかで、もうひとつ課題となったのが、過去の施業履歴の収集だった。
「施業履歴を図面として残していなかった山主さんも多かったので、森林組合にも協力を仰ぎながら、地道にデータを集めていきました。それでも、やはり正確な施業履歴が見つからなかった森林もある。最終的に実施地面積として認められたのは、当初見込んでいた面積の7割程度でしょうか」。
無理なくはじめて
大きく育てていけばいい

成功への一番の近道は少しずつでも実績を作ること
山林所有者の合意形成と、正確な施業履歴の収集。森林クレジットに取り組む上で、多くの事業者が直面するふたつの壁だと言えるだろう。ただし、それを一気に乗り越えようとする必要はない。松山さんが強調するのは「はじめてみること」の重要性だ。
「プロジェクトの対象森林は、あとから計画変更を経れば追加することができます。まずは実績をつくり、その上で改めて所有者に交渉していけばいい。それが一番の近道だと思います。私たち自身、そうやってプロジェクトを育てていくつもりです」。
2024年度末時点で、3708haの登録面積を確保する吉野林業プロジェクト。16年間を通じて毎年毎年平均3100t-CO₂のクレジットの創出を見込む。今後もさらにその範囲と規模拡大を検討しながら、クレジット売買の収益を、森林経営活動に再投資していく予定だという。
無理なくはじめて、大きく育てる。森林クレジットという複雑な制度を前に、思わず立ちすくんでしまいそうになったときこそ、この言葉がきっと勇気をくれるはずだ。
吉野林業プロジェクトから学ぶ
森林クレジット創出のヒント

できる範囲から無理なくはじめる
森林所有者の数が少なくても、特に所有者が高齢者の場合は、永続性担保措置が心理的なハードルになることも。また、そもそも所有者が森林クレジットを理解しきれていないことも少なくない。だからこそ、まずは無理なくスタートし、わかりすい実績を示していくことが重要になる。
地域の伝統をブランディングとして活用
「吉野林業プロジェクト」の強みのひとつは「吉野林業」という伝統ある言葉を、プロジェクト名に冠したことにある。これにより、企業側にとってもクレジットを購入する動機が明確に。地域で育まれてきた歴史や伝統をブランディングに活用することが、クレジットの販売につながる。
必要書類の準備はなるべく余裕を持って
森林クレジットが普及するなか、審査費用を支援する補助金の需要も急増している。そのため、補助申請の受付から日をおかずに、予算枠が埋まってしまうことも。制度事務局のHPをこまめに確認しながら、余裕を持って必要書類の準備を進めておこう。
PROFILE
(一社)大和森林管理協会 事務局長
松山充さん

取材・文:福地敦
FOREST JOURNAL vol.24(2025年夏号)より転載