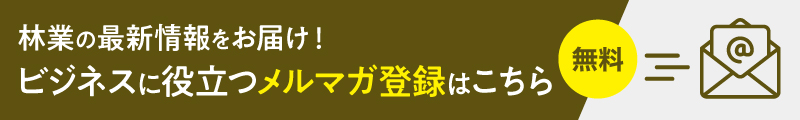いかにクレジットの創出・販売を実現したのか? 森林クレジットの先駆者から学ぶ活用のヒント
2025/02/03

全国でもいち早く、2014年から森林クレジットの本格的な販売に取り組んできたのが、根羽村森林組合だ。30名を超える所有者の合意を取りつけ、いかにJクレジットの創出・販売を実現したのか。同組合で総務課長を務める大久保裕貴さんにお話を伺った。
トップダウンの意志決定で
スタートダッシュが可能に
長野県の南端に位置する根羽村。村の総面積の92%を占める森林を管理する根羽村森林組合は、いち早く森林クレジットの活用に乗り出した事業体のひとつだ。
「根羽村では、すべての村民が山林の所有者であり、組合員でもあるんです」。そう教えてくれたのは、同組合の大久保裕貴さんだ。
そのため林業経営に熱心な所有者も多い一方で、木材価格の低迷が続くなか、親世代から引き継ぐ山林を「負の遺産」と感じる現役世代も増えはじめていたという。
「山主のみなさまに、少しでも多くの利益を還元する方法はないだろうか。そう考えていたときに、環境省が主催するJ‐クレジット制度の説明会に参加したんです。2014年の8月のことですね。」
そこからの動きが速かった。組合員がトップダウンでJ‐クレジット制度の活用を意思決定すると、同年の10月には組合員に向けての説明会を実施している。
「当初は『吸収量取引』と言っても、なかなか理解してもらえなかったので、具体的な数値なども用いながら、丁寧に説明していきました。最終的には、ほとんどのみなさまが『組合がやることなら、きっと大丈夫』と、前向きに受けとめてくれました」。
山主への利益還元はもちろん
さまざまなメリットも
その後、森林経営計画をもとに候補地を絞り込み、最終的に選ばれたのが56haの森林だ。所有者は36名と決して少なくはない。林班計画に分類される森林でクレジットの創出を行うには、各所有者との覚書の締結といった事務的な手間が増える傾向にある。それでも「より多くの山主に利益を還元する」という当初の目的を達成すべく、労を惜しまず所有者一人ひとりの同意を取り付けていった。
「そこからは、ひたすら地道な事務作業ですね」と大久保さん。通います」と大久保さん。
通常業務の合間を縫い、審査期間ともやりとりしながら、コツコツと必要な書類を作成していった。
2016年12月にはプロジェクトの認証を受け、翌年4月から本格的にクレジットの販売を開始。仲介業者の支援もあり、これまで取引のあったハウスメーカーや金融機関などを中心に、着実に販売実績を重ねていった。発行した240トン分のクレジットは、2020年までにほとんどを売り切り、トータルで約113万円を山主に還元することができた。
「クレジットの販売を通じて、これまで出会うことがなかった業界・業種の企業とのつながりが生まれ、根羽村の“関係人口”が広がったこともメリットだと感じています」と大久保さんは語る。
また先進的な取り組みに挑む組合として注目度が高まり、視察や取材が増えたことで、職員のエンゲージメント向上したという。
「決して規模が大きいとは言えないウチの組合でも、クレジットを創出・販売することができました。たしかに実務上の苦労はあるかと思いますが、審査期間や関連省庁など、相談すれば力になってくれる人は必ずいるはずです。まずは、やってみること。それが何よりも重要だと感じています」。
【取り組みの効果】
● 取引先企業 12社増加
● 森林所有者への還元 約113万円
● 視察・問い合わせ数 30件以上
● 意見交換会の開催による同業・異業種とのつながり増加
● プロジェクトを通じた職員の意識向上

根羽村森林組合から学ぶ
森林クレジット活用のヒント
01 なるべく多くの所有者に
森林クレジットを理解してもらう
クレジット認証の対象となる森林の所有者だけでなく、できるだけ多くの組合員を対象に説明会を実施。「クレジットの創出」という森林の新たな価値を理解してもらうことが、スムーズな合意形成にもつながる。
02 クレジットの販売は、
小口でもコツコツ積み重ねて
一回の取引量は数トン程度であったとしても、毎年継続して購入してもらうことで、結果的にはまとまった量のクレジットを販売することができる。取引企業と長期的な関係性を構築していくことを目指そう。
03 視察や取材の依頼は
できるだけ積極的に受け入れよう
森林クレジットの販売を通じて、業界内での注目度が高まると、視察や取材の依頼も増えるはず。認知度が向上すれば、新たな販売先が見つけやすくなるだけでなく、職員のエンゲージメントも高まっていく。
問い合わせ
根羽村森林組合
長野県下伊那郡根羽村407-10
TEL:0265-49-2120
文:福地敦
FOREST JOURNAL vol.22(2024年冬号)より転載