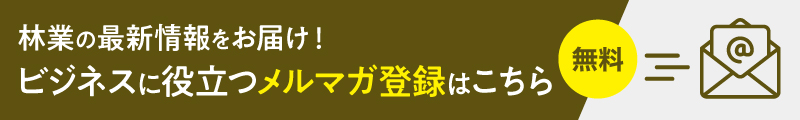【木青連座談会】国産材の価値向上にどう取り組む? 川上・川中・川下の連携と現状の課題
2025/10/22

全国の木材産業に携わる青壮年約800人が集う「木青連」(日本木材青壮年団体連合会)。今回、森林から住宅まで、木材の流通における川上・川中・川下それぞれの立場から4名の方にお集まりいただき、業界の課題と未来についてお話しいただいた。
1.各分野が抱える課題とは
2.木材の価値向上に向けた取り組み
3.持続可能な林業・木材業界に向けて
4.青壮年が集う「木青連」ってどんな団体?活動内容や展望を聞きました。
5.一緒に木材業界を盛り上げましょう!
昭和31年に発足、今年で69年を迎える木材業界の青年団体。会員は810人ほどで、林業会社から工務店まで、木材に関わる全ての業種の人が在籍しており、30代後半から40代前半の方たちが中心に活動をしている。全国の木材産業に携わる青壮年経営者の交流と親睦を通じ、相互の啓発に努め、知識、品位の向上を図る。また、木材・林業に関する社会的な普及啓発活動などを行うことによって木材産業の近代化に寄与し、社会に貢献することを目的としている。
座談会参加メンバー
川上
沖中造林株式会社
代表取締役
沖中 祐介さん

三重県で明治11年から続く、自伐林家の6代目。約千ヘクタールを管理して造林・育林から伐採・搬出までを行う。樹齢100 年超のスギ・ヒノキを育て、神社仏閣用の注文も受けている。
力を入れていること:「“かっこいい林業”を発信すべく、女性の現場作業員を入れたり、朝4時から働くサマータイムを導入したりと、他社が行っていない取り組みを積極的にしています」。
川中
肥後木材株式会社
代表取締役
佐藤圭一郎さん

創業68年目の、熊本県で原木市場と製品市場の運営、プレカット加工を主に行う木材会社の4代目。
力を入れていること:「今年から新事業を始めて、本社に乾燥加工設備を作り、乾燥機がないまたは増設できない地元の中小製材所と協業して品質の確かなKD材を生産しています。国産材の安定供給に寄与していこうという思いで取り組んでいます」。
川中
牧野木材工業株式会社
専務取締役
牧野 泰斗さん

江戸時代末期の創業から数えると163年目を迎える製材所を岡山で営む。ヒノキの製材が90~95%を占めており、一般的な住宅用の柱や土台などを製材している。
力を入れていること:「JASの「機械等級製材」です。含水率や強度計算をしっかりと測定し、1本1本に安全性の高い、信頼のおける製材を提供しています」。
川下
株式会社国興
代表取締役
田中 一興さん

創業91年。製材業を祖業とし、現在は長野県松本市で木造住宅を中心とした工務店を営む。他にもショールームやオフィスに木を植え、街の中に森を作るような取り組みをしている。
力を入れていること:「環境との共生を意識した家づくりに取り組んでいます。信州の気候に合わせて、居心地の良い、ここにいたいと思えるような性能・素材・デザインにこだわっています」。
各分野が抱える課題とは
――それぞれの立場から見た木材業界の課題について聞かせてください。
沖中 林業は地域によって樹種もやり方もまったく違うのが現状です。国の政策では大量伐採を行い、再造林などの作業のスマート化を推進しようとしていますが、地域での浸透はまだまだ。各社のやり方が違う中で、方向性を統一していくのは難しい課題です。また、三重県ではバイオマス工場が急激に増えており、地元の製材所との需要バランスが崩れています。需要と供給のバランスが価格に直結するため、適正価格と言われても、一次産業側からすると全然適正じゃない。川中・川下の方も苦労されているのはわかるので、「もっと高く買ってくれ」とは言えないジレンマがあります。
佐藤 木材が高く買われない最大の原因は、住宅需要に依存しすぎていることです。住宅が落ち込めば業界全体の動きが悪くなる。一方で、原木は15年前とは状況が変わり、製材需要以外にも合板、バイオマス燃料、丸太輸出など多様な需要が生まれ、底値が上がってきました。製品についても非住宅需要や製品輸出を増やし、住宅の波を吸収できる体制を作る必要があります。店舗、学校、ビル、病院、畜舎など、木造建築の用途は確実に広がっていますが、その割合を増やす必要があるのではないでしょうか。
田中 住宅需要については、最終的にエンドユーザーとなる住宅の施主が最もコストを重視する傾向が確かにあります。環境意識や県産材への関心を持つお客様もいますが、「なんとかコストを抑えたい」「将来が心配」という声が多い。昔は融資を受けられる額全部使って家を建てていましたが、今は借りられてもローンを上限まで組みたがらない方が多い。県産材・国産材と輸入材の価格差をどう埋めるかが壁ですね。木を使う意味や魅力を伝え、価格優位の事業者との差別化を図る必要があります。
牧野 製材所は原木市場と製品市場の間で、2つのマーケット原理に挟まれています。原木は、「10本切るのが大変だから1本2500円」という具合に、量が多くても単価が下がらない。一方で製品は通常のマーケット原理で、「たくさん買うから安くして」となる。この非対称性が経営を圧迫しています。また、3K(きつい・汚い・危険)といわれる業界で人材確保が困難です。従業員にしっかりした給料を出せるマーケットにしていきたいのですが、造林業は「緑の雇用」などの支援があるのに対し、製材所や建築関係には支援がありません。そこも大きな課題ですね。
木材の価値向上に
向けた取り組み

――国産材の価値を高めるためには、どのような取り組みが必要だと思われますか。
沖中 エンドユーザーに木材やその魅力について知ってもらうことだと思います。工務店の担当者レベルでスギとヒノキの違いがわからないケースもあります。そこで、弊社では「大黒柱ツアー」を実施し、お客様に山で木を切るところから製材までを1日で体験してもらっています。2019年には、1本の丸太からカヌーを作り、ウッドデザイン賞もいただきました。建築以外でも木の魅力を伝える取り組みが必要と感じています。
田中 それは素晴らしい取り組みですね。県産材・国産材を使った家と新建材を使った家では、実際に体感すると違いがわかります。「なんか心地がいい」という感覚的な良さを体験してもらうことが重要ではないでしょうか。無垢材に手を置いた時と人工素材に手を置いた時で「ストレス度が違う」というエビデンスも出ています。
牧野 無垢材とプリント材の違いを一般の人が見分けられないのも問題ですよね。本物の木を使った空間の良さを体験してもらえれば、高くても本物の木を使おうという気持ちになってもらえるはず。
佐藤 皆さんのお話を聞いて、体験の重要性を感じました。そのためには、品質向上が絶対条件です。輸入材と国産材の品質差を埋め、強度と寸法の安定した製品を作ることで、国産材のシェアを高めていけるのではないでしょうか。
持続可能な
林業・木材業界に向けて
――100年、200年続く持続可能な業界にするために何が必要だと思われますか?
沖中 実は林業はもう既にサステナブルなんです。弊社が147年続いているのがその証拠です。ただ、注意は必要です。現在の再造林率は40%程度で、60%は植林されていません。これでは持続可能とはいえない。山の所有者に木の魅力を伝え、「山なんていらない」ではなく、昔のように山を投資対象として見てもらう必要があります。育てる魅力を伝えることが大切だと思います。
牧野 確かに、木材は昔から人に寄り添ってきた素材で、本来サステナブルですよね。ただ、先細りしないよう魅力的な業界だということを発信していく必要はあるのではないでしょうか。
田中 林業自体がサステナブルというのはその通りです。同じ木は1本もないので扱いが大変ですが、それに対していろんな知恵を絞って使ってきた、業界の価値を改めて感じています。
佐藤 皆さんのお話はもっともですが、私にとっては、担い手不足が最大の問題です。人がいなければ会社も成り立ちません。職場環境の整備と適正な賃金の確保が必要ですが、そのためには利益を出せる業界にしなければいけないのではないでしょうか。川上・川中・川下が連携し、この大きな課題に取り組んでいきたいです。
青壮年が集う「木青連」ってどんな団体?
活動内容や展望を聞きました。Q.どんな活動をしているのか?
A.大きな事業は2つのコンクールです。会長・長谷川さん:1つは全国の小中高生を対象にした木工工作コンクールで、50年間続いています。毎年2万点もの作品が集まっています。
もう1つは木材活用コンクールです。木材をうまく使った建築や木製品を表彰しています。
その他にも災害時の支援活動も行っており、応急仮設住宅用の木材を提供する協定を結んだり、プレカット業者同士で助け合うネットワークも作っています。
関係省庁や業界団体との情報交換会、「共生社会」をテーマにした勉強会、DXセミナーなどを開催しています。
Q.木青連の魅力や参加するメリットは?
A.会社の大小だけでなく、地域の垣根を超えた交流ができます沖中造林株式会社 沖中さん:全国に仲間がいるので、他県の取り組みを見学しやすくなりました。以前、高知県の林業会社を見学させてもらい、やり方を教えてもらうなど、同業者間でのノウハウが共有できています。
肥後木材株式会社 佐藤さん:実際に仕事につながったケースも多々あります。現在の取引先を見ると木青連の仲間との取引が非常に多く、サプライチェーンとして機能しています。
株式会社国興 田中さん:県外の加工が必要な時に仲間で使っているSNSで相談すると、すぐに「うちでできるよ」と言ってもらえます。補助金の情報共有やコンサルの紹介も受けられ、製材工場の改修もその補助金でできました。
牧野木材工業株式会社 牧野さん:さらに、各地域で生えているヒノキの色や特性についてなど、会社の大小や業種にかかわらず、知識の交流ができるのが本当に良いところです。
Q.今後どのような取り組みをしていきたい?
A.川上から川下と様々な仲間との連携で、木材の価値向上と業界を盛り上げていきたい株式会社国興 田中さん:800人以上の仲間と密に連携していけばサプライチェーンが強化できます。災害連携やプレカットなど、既に始まっている取り組みを発展させ、会員同士の交流を深めていきたいです。
牧野木材工業株式会社 牧野さん:静岡に木青連の山があるのですが、そこから切った材で「木青連の家」を建てて定期的に会議を開くなど、川上から川下までを網羅したプロダクトを作ってみたいですね。木造建築が50年経っても朽ちずに利用できることを実証する象徴にしたいです。
肥後木材株式会社 佐藤さん:地元だけで活動している会員にも、地区の集まりや全国大会に参加してもらい、幅広い交流を通じて仕事にもつながる関係を築いてほしいと思います。
沖中造林株式会社 沖中さん:川上から川下までさまざまな会員がいるので、「うちの木が田中さんの建てる家で使われる」といった、顔の見える流通ができれば最高です。
一緒に木材業界を盛り上げましょう!
〈木青連 会長〉
株式会社長谷川萬治商店 代表取締役長谷川 泰治さん
日本木青連は、林業から工務店・木製品販売まで川上から川下の多様な仲間が集う木材業界では唯一の場です。多様性に溢れる仲間が集まり、ともに学び合い業界の未来を創る力を実感できます。林業に携わる皆様の日本木青連へのご参加を心よりお待ちしています。一緒に木材業界の未来を創っていきましょう。
〈木青連 監事〉
伊太祁曽神社 禰宜奥 重貴さん
木の神様を祀る伊太祁曽神社の禰宜として、木青連とそれ以外の方々をつなぐハブ的役割を果たしたいと考えています。伝統文化も木材業界も、守るだけでなく変化を恐れず「攻めながら守る」姿勢が大切。木材業界の方々との関係を深め、業界の発展を通じてより良い社会の構築に貢献したいと考えています。
文:笹間 聖子
写真:井 ひろみ
FOREST JOURNAL vol.25(2025年秋号)より転載